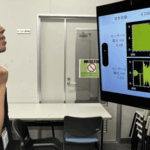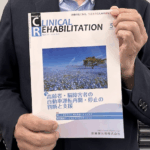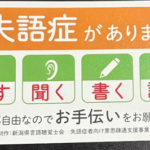 2026.01.08
2026.01.08
吉岡先生が新潟県阿賀町で講演を行いました.
<どういう経緯で講演をすることになったのですか?>
阿賀町役場にあるこども・健康推進課の依頼を受けて、2018年度から言葉の相談会を開催しています。最初は年4回でしたが、その後年5回、6回となり、2025年度は年8回の開催となります。子どもの数が少ない阿賀町ですが、相談回数が多くなったのには理由があります。一つは相談に行く施設が近くにないこと、もう一つは小中学生からのニーズが出てきたことです。相談会のモットーは、できるだけ定期的に訓練に通わずホームトレーニング指導で治すことですので、必然的に経過観察期間が長くなります。
私は依頼されたお子さんを診て指導するだけですが、保育士、養護教諭、小中学校教諭、保健師、児童クラブ指導員の方々は、何歳頃にどういう状態であれば相談した方がよいのか判断がつかないので、大まかな目安が欲しいとのことで講演をすることになりました。
<内容は?>
参加したのは阿賀町で働く保育士、小中学校教諭、養護教諭、児童クラブ指導員、保健師など35名でした。
講演内容はこれまで行ってきた言葉の相談会を振り返り、相談時の年齢は4~5歳代が多いこと、発音に関する訴えが最も多かったことを報告しました。それを踏まえて、4歳になっても「カ」行が言えなかったら相談会に回して欲しい、文字言語については、5歳頃に「おかし」と聞いて「お・か・し」のように3つの音に分けられるか、などを確かめて欲しいと伝えました。
<在学生・高校生へメッセージ>
言語聴覚士に限らず医療従事者は医療機関などに来た人だけを診ています。しかし、発音の問題や言葉の遅れに気づかれずにいると必要な支援を受けられないことになります。そのような事態に陥らないためにも、言語発達に関する啓発活動は必要です。お子さんが生まれれば親御さんは育児をしますので、子どもの成長については経験で語ることができます。育児の経験を主張されれば、私たちは親御さんを説得することが難しくなります。しかし、経験を越える知識で地道に支援を続けて行くことが言語聴覚士には求められています。
少子化の時代ですが、対象となるお子さんが減ったという印象はありません。子どもの未来を一緒に切り開きませんか。

吉岡先生,ありがとうございました.病院などでの勤務だけでなく,こういった啓発活動も言語聴覚士の重要な役割ですね.
**********************************************
STは、言語聴覚士のことで,コミュニケーションとのみ込み(嚥下)を支える医療系国家資格のいる職業です。Speech-Language- Hearing Therapistsの略です。
新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の言語聴覚学科広報より ST kouhouがお送りしました。