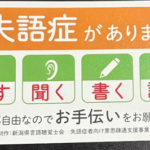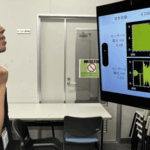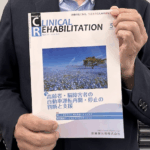2026.02.10
2026.02.10
こんにちは。STkouhouです。
言語聴覚士が行う臨床業務の一つに,摂食・嚥下訓練があります.
摂食・嚥下訓練とは,食べ物を噛んだりのみこんだりする摂食・嚥下機能に障害を持つ方を対象に行う訓練です。
最近,摂食・嚥下機能に障害を持つ方とそのご家族のニュースをみつけました。
障害を持つ方はまだ30代の男性ですが,不整脈のため心肺停止の状態に陥り,一命はとりとめたものの,3年経つ現在も認知面や運動面に重い障害が残存しています。
奥様のそらさん(@soraeureca)は,介護の日々を漫画にしてInstagramに投稿されています。
奥様は仕事をしながら,毎日病院に出向き介護をされています。その献身的な姿勢には本当に頭が下がります。
この方への認知面や運動面への障害にアプローチするリハビリ職の活躍も,注目すべき点です。
本学科の学生が目指す言語聴覚士も活躍しています。この方を担当されている言語聴覚士は,摂食・嚥下訓練のシーンでよく登場しています.
嚥下障害がある場合,そのときの嚥下機能に合った訓練食を用いて訓練を行います.

嚥下機能を重視して安全第一に嚥下食を用意すると,いつも似たような形状や味のものばかりを使用することになりがちです。
しかしこの方を担当されている言語聴覚士は,嚥下機能のみにとらわれず,患者さんの好みや味の濃さなどを考慮した上で,様々な訓練食を準備しているようです.その姿勢は単なる訓練を超えて,患者さん自身の食べる喜びを追求したものになっています.
患者さんの機能を向上させることだけでなく,食事の楽しみも意識した訓練は,本学が理念として挙げる「患者さんのQuality of Life(生活の質)をサポートする人材を育成する」と通じるものです。
そらさんは,発症から1年間で一番嬉しかったこととして,口から食べ物を摂れるようになったことを挙げています.
このエピソードをみると,改めて言語聴覚士とは良い仕事だなと,しみじみ実感します.
そして本学科の卒業生も,この言語聴覚士のような人材であってほしいと願います。
言語聴覚士が関わる領域は多岐にわたりますが,コミュニケーションと食事の2つの領域に分類することができます。
どちらの領域も,その人自身の尊厳に関わる点が共通しています。
コミュニケーションや食事へのアプローチを通して,患者さんへの全人的な医療を行う言語聴覚士,
関心がある方はぜひ本学科への進学をご検討ください!
[su_button url="https://www.nuhw.ac.jp/faculty/medical/st/" target="blank" style="flat" background="#2dceef" color="#f7f8f5" size="8"]言語聴覚学科の紹介はこちら[/su_button]